一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利
野村萬斎のややこしやとは何か

「ややこしや」は、NHKの子ども向け番組「にほんごであそぼ」で大きな人気を集めた、野村萬斎さんによるユーモラスな狂言のパフォーマンスです。
ややこしやが生まれた背景とエピソード
「ややこしや」は元々、狂言の持つ言葉遊びや混乱をユーモラスに描く伝統をベースにしています。野村萬斎さんは「にほんごであそぼ」の企画に参加する中で、現代の子どもたちにも分かりやすく、楽しく日本語の奥深さを伝える方法を模索していました。その流れの中で、「ややこしい」状況や表現をコミカルに織り交ぜた「ややこしや」が誕生しました。
この演目は、元々の狂言「まちがいの狂言」からヒントを得ており、物事がごちゃごちゃになった様子や、聞き間違い、思い違いなど、日常に潜む「ややこしさ」がテーマです。萬斎さん自身も、稽古の中で子どもたちの反応を取り入れながら、今の「ややこしや」のスタイルを作り上げていきました。
にほんごであそぼでのややこしやの位置付け
「にほんごであそぼ」における「ややこしや」は、番組の人気コーナーの一つとして定着しています。このコーナーでは、野村萬斎さんが軽快なリズムに合わせて言葉のややこしさをコミカルに表現します。
狂言の伝統をベースにしつつも、子どもたちが日本語の面白さに親しめる工夫が随所に凝らされています。ややこしい言葉やフレーズが繰り返されることで、視聴者も自然に耳に残り、日本語の奥深さやリズム感を楽しむことができます。教育番組ならではの分かりやすさと、萬斎さんの魅力が融合したコーナーです。
狂言の伝統とややこしやの関係
「ややこしや」は、狂言の中でも特に「誤解」や「まちがい」をテーマにした作品から発想を得ています。狂言は、室町時代から続く日本の伝統芸能で、滑稽なやり取りや言葉遊びが見どころの一つです。
「ややこしや」が取り上げるのは、誰もが経験するような日常の混乱や曖昧さです。こうしたテーマは、古典狂言でもたびたび描かれてきました。萬斎さんは、その伝統を現代の感覚に合わせて表現し、子どもから大人まで笑いながら楽しめる形にアレンジしています。「ややこしや」は、古典芸能の奥深さと現代的なユーモアが見事に融合した作品です。
映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう
映画「国宝」の原作の「下」はこちら。
ややこしやを演じる野村萬斎の魅力
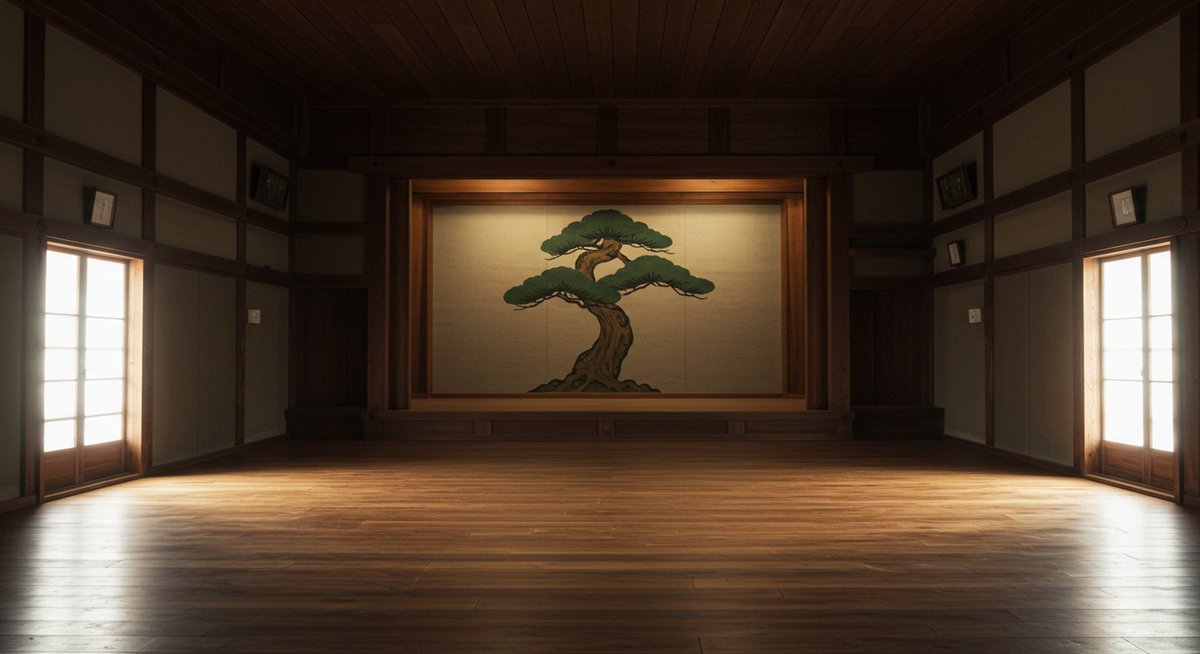
野村萬斎さんの「ややこしや」には、彼ならではの表現力や存在感が存分に発揮されています。その魅力について詳しく見ていきましょう。
独自の表現力と舞台での存在感
野村萬斎さんは、舞台上で圧倒的な存在感を放ちます。表情豊かな動きや声の抑揚を巧みに使い分け、観客を一瞬で物語の世界へ引き込みます。特に「ややこしや」では、ちょっとした言葉のやりとりや、体の細かい動きまでユーモラスに演じ分けています。
萬斎さんの表現力は、狂言師としての長年の経験や訓練に裏打ちされています。緻密な演技と、観客との息の合ったやりとりで、子どもたちにも分かりやすく、飽きさせない魅力を生み出しています。
ややこしやで感じる野村萬斎のユーモア
「ややこしや」で特に感じるのは、萬斎さんの持ち味であるユーモアです。難しい言葉や複雑な状況も、萬斎さんの手にかかれば、思わず笑ってしまう楽しいやりとりに変わります。
たとえば、同じ言葉を何度も繰り返すシーンや、ややこしいフレーズをリズミカルに並べていく場面では、萬斎さん自身も楽しそうに演じています。その空気感が観客にも伝わり、子どもだけでなく大人も思わず夢中になってしまいます。
狂言師としての野村萬斎の経歴
野村萬斎さんは、現代を代表する狂言師のひとりで、数多くの舞台で主役を務めてきました。幼い頃から能楽の家に生まれ、伝統芸能の世界で育った彼は、狂言の技術と精神をしっかりと受け継いでいます。
また、伝統的な狂言だけでなく、映画やテレビドラマ、現代劇への出演も多く、多彩な分野で活躍しています。そうした経験が、「ややこしや」のような新しい試みにも柔軟に生かされているのです。
\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/
数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!
まちがいの狂言ややこしやの人気の理由

「ややこしや」は、子ども向け番組発の楽曲やコーナーでありながら、幅広い世代からの人気を集めています。その理由を探っていきましょう。
子どもから大人まで楽しめる内容
「ややこしや」は、言葉の面白さを誰もが楽しめるように工夫されています。複雑な言い回しやユニークなリズムで、子どもたちは笑いながら日本語の響きやリズムを体験できます。
一方で大人にとっては、日常生活にも通じる「ややこしさ」や言い違いの面白さ、そして狂言の伝統に触れるきっかけにもなっています。このように、年齢を問わず楽しめる点が人気の大きな理由の一つです。
楽曲や映像作品としてのややこしや
「ややこしや」は、楽曲としても親しまれています。番組内で流れるリズミカルな音楽や、萬斎さんによる独特の言い回しが印象的です。音楽CDや配信サービスで視聴できるようになっており、子どもたちの間でも人気のフレーズになっています。
また、映像作品としてもYouTubeやDVDなどで繰り返し鑑賞されています。映像で見ることで、萬斎さんの細やかな表情や動きも楽しめるため、さらに魅力が伝わりやすくなっています。
SNSやメディアでのややこしやの広がり
「ややこしや」は、SNSやネットメディアでも広がりを見せています。放送や動画配信を通じて、子どもたちや保護者が感想を発信し、さらに人気が広まっています。
特にSNSでは、「ややこしや」を真似した動画やイラストが投稿されるなど、ファン同士の交流も活発です。テレビや配信だけでなく、さまざまなメディアを通じて新しいファン層が増えています。
小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!
能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。
狂言ややこしやをもっと楽しむためのポイント

「ややこしや」をより深く楽しむためには、言葉遊びや表現を積極的に味わうことが大切です。ポイントごとに見ていきましょう。
ややこしやの言葉遊びを味わうコツ
ややこしやの最大の魅力は、ややこしい言葉のやり取りにあります。楽しむコツは、早口言葉のように実際に声に出してみることです。音の響きやリズムを感じながら、どこがややこしいのか比べてみてください。
具体的には、以下のように楽しめます。
- 何度も繰り返して発音してみる
- 家族や友人と一緒に真似し合う
- どの部分が面白い・難しいか意見を出し合う
こうした体験を通じて、言葉の面白さをより身近に感じることができます。
実際の舞台や映像を鑑賞する方法
「ややこしや」をより臨場感たっぷりに楽しむには、実際の舞台や公式映像を鑑賞するのがおすすめです。萬斎さんの舞台公演は、公式サイトや各地の劇場情報で日程を確認できます。
また、テレビ番組やDVD、動画配信サービスでも「ややこしや」を観ることができます。特にNHKの「にほんごであそぼ」公式サイトや関連YouTubeチャンネルで、萬斎さんのパフォーマンスを手軽に楽しむことができます。自宅でも迫力ある表現に触れられます。
オリジナルのややこしやを作ってみよう
「ややこしや」の楽しさを自分でも体験したい場合は、身近な言葉や状況を使ってオリジナルの「ややこしや」を考えてみるのがおすすめです。たとえば、家族で「ややこしいこと」をテーマに短いフレーズを作り合ってみると、さらに盛り上がります。
作る際は次のポイントを取り入れると楽しくなります。
- 同じ言葉や似た言葉を繰り返す
- 聞き間違いや勘違いを盛り込む
- リズムやテンポを工夫する
自分だけの「ややこしや」を作ることで、言葉遊びの幅もぐっと広がります。
まとめ:ややこしやを通じて感じる野村萬斎と狂言の奥深さ
「ややこしや」は、日本の伝統芸能である狂言のユーモアや言葉遊びを、現代の子どもたちにも親しみやすく伝える素晴らしい作品です。野村萬斎さんの豊かな表現や舞台での存在感、そして親しみやすい演出により、幅広い世代に愛されています。
この作品をきっかけに、狂言や日本語の奥深さに興味を持つ人が増えているのも特徴です。実際に観たり、言葉遊びに挑戦したりすることで、芸能の楽しさを身近に感じることができます。「ややこしや」は、伝統と新しさが調和した、魅力あふれる文化体験の入口となっています。
能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!















